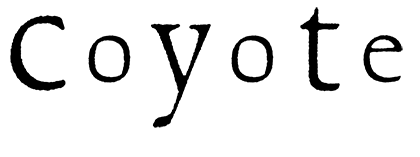文/松家仁之・写真/赤阪友昭
一階の奧の部屋で寝起きしているクリフォードは早起きだ。朝5時、起床。まず自分のコーヒーを淹れる。そしてタバコを一服。
就学前の幼児がたくさんいるので、子どもたちが起きだしてくれば、騒いだり泣いたりして、にぎやかだ。子どもたちとその家族が二階に並ぶ寝室にあがり、寝静まっているあいだが憩いの時間なのかもしれない。
朝食はクリフォードの担当である。毎晩、眠るまえに、サワドウのパン種の入ったポリバケツに小麦粉と水を足し、ゆっくりかきまぜておく。翌朝には発酵がすすんで、小さなプツプツした泡が立っている。フライパンを熱し、つぎつぎに焼いてゆく。バターとメープルシロップをたっぷりかける。ふつうのパンケーキは二枚も食べたら飽きてしまうが、サワドウのパンケーキは絶妙な酸味とねばりがあって、食べ飽きない。
朝食の準備を終えると、クリフォードはおいしそうにコーヒーを飲む。
「きみもコーヒーが好きか? それはいい」
コーヒーを飲んでいれば機嫌がいい。
昔は島の北部の浜辺が自然の飛行場だった。小さな郵便飛行機が週に一便だけやってくるようになり、滑走路が整備された。星野道夫の最初の訪問も、郵便飛行機に乗せてもらってのものだった。
クリフォードは昔、無免許でセスナ機を操縦し、空を飛んでいたという。「そんなのは、あたりまえのことさ」と笑う。
19世紀末に教会の宣教師が村に導入したトナカイの放牧をクリフォードは父から引き継ぎ、さらに成功させて、セスナ機を購入する資金を得たそうだ。無線はクリフォードの家にしかなかったから、遭難の無線を受信すると、自分のセスナを飛ばして捜索に向かい、人を助け出したこともあるという。
娘のティナは父譲りで機械に強い。スノーモービルを運転し、スマートフォンを使い、タブレット端末で写真を撮る。フェイスブックもやっている。20歳のころ、星野道夫が村長宛に出した手紙が、翌年になって返信された時代は、もはやはるか昔の話だ。
歩いて3分のところに教会の墓地がある。クリフォードの両親と祖父母はここに、近年亡くなった妻のシュアリーの墓は本土にある。

キッチンの主役はつねに、クリフォードである。毎晩、サワドウの酵母菌に、水と小麦粉を足し、かきまぜる。翌朝には充分に発酵が済んでいて、これで極上のサワドウ・パンケーキを焼くのだ。白いバケットには「吐き気がするような匂い」と星野道夫が書いた伝統の調味料シールオイル。

部屋の真ん中にあるオイルストーブは、ひと晩じゅう焚かれているので、暖房も兼ねている。子どもたちがTシャツで過ごせるほど暖かい。朝も昼も晩も、三家族が入れ替わり立ち替わり食堂のテーブルに着いて、ばらばらに食べる。クリフォードは黙々とパンケーキを焼く。