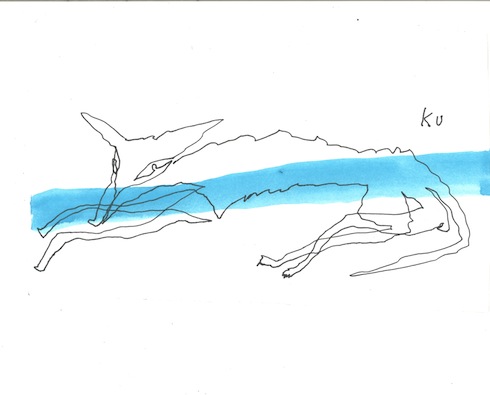
Essay vol.10
再訪 野坂昭如 第6回「泉鏡花をめぐる」
長い闘病から立ち直った時に寂聴にある知らせが飛び込んできた。短篇集『風景』で2011年度の第39回泉鏡花文学賞を受賞したのだ。
「小説は面白くなければいけない。読む人を幸福するのは小説。90歳になってようやく書くことに自信が出てきた」
寂聴の授賞式のスピーチだった。
「想定外のことが起こるのが世の中、矛盾を考えるのが哲学、書き表すのが文学。新鮮な賞をいただいた。こうなれば百歳まで生きようと思います。百歳で芥川賞をいただきたいです」
人はなぜ小説家になるのか、『風景』には寂聴の大切なモチーフがあった。寂聴は作家の生成をこの短篇集で誠実に語っていったのだ。例えば安吾賞受賞とともに、かつての破滅的な恋と死が胸に蘇る「デスマスク」。闇屋が跋扈し、配給を求める人々が列をなす昭和21年、敗戦直後の日本を舞台に、親を失い、子を失い、生きるための指針を失い、焼け野原に立ち尽くす人々の顔は暗く沈んでいる。そんな時代に現れたのが坂口安吾『堕落論』であった。人は堕ちる。人間だから堕ちる。堕ちればこそ、救いが見える。力強く響くその言葉は、人々に生きることへの覚悟を与えた。混迷の時代にあって求められる確かな言葉、安吾が説いたその言葉を、寂聴が引き継いでいく。いまこそ堕ちよ。そして生きろと寂聴は書く。その姿勢は野坂昭如にも通じるものがある。
2002年には野坂昭如も『文壇』という作品で泉鏡花賞を受賞していた。しかも受賞の理由はその作品だけではなく、「およびそれに至る文業」と冠されていた。野坂の文学の軌跡を追ったのか、寂聴が話題を提供するように口を開いた。
「『四畳半襖の下張』の裁判で負けていくら取られたの?」
寂聴は野坂に訊ねた。1972年責任編集した月刊誌『面白半分』に永井荷風の『四畳半襖の下張』を掲載し、わいせつ文書販売の罪に問われたのだ。
「5万円」
「あの当時でもそんなに高くないでしょう」
「高い」
「高くないでしょう。煙草と酒をやめたらすぐにでもできる」寂聴は続けた。「永井荷風の小説、あれが一番面白い」
寂聴は野坂の先駆的な役割と批評眼の正しさを讃えた。
「荷風はお好きですか?」
寂聴の質問に野坂は何も答えない。
「野坂さんは優しい人です。当初野坂さんは派手な人だと勝手に思い込んだ。深刻なことは避ける人だと思ったが、戦争をモチーフにした小説は小さい子を主人公にして悲しみを描いた。本当に涙が出る。いろいろな苦労をして書かれている方」
「パパ、いかがでしょうか」夫人が声をかける。
「優しい?」寂聴が訊ねる。
「ありがとう」野坂がゆっくりと答えた。
「でも私、一つ奥さんの気持ちがわかるのは、誰にでも優しいの。人間みんなに優しいの」
「そう、他人には優しいです」
寂聴の言葉に夫人は背中を押されたように語気を強めた。野坂昭如の人生は愛だという言葉を考えた。
「愛は優しいということです」寂聴が言った。
野坂にとって寂聴はどういう存在か、僕が訊ねた。
「優しい」
野坂は表情を変えず小さく答えた。
